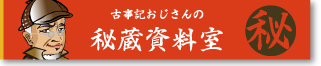

最初に生まれたグループは家屋に関する神々のようです。 その中で注目しておいて頂きたいのが 大屋毘古神(おほやびこのかみ)です。 ずっとあとになりますが、この神のところにヤソガミ達に追われたオホナムヂ(後のオオクニヌシ)が … 続きを読む →
前回までで別格の神様を紹介し、登場理由を説明しました。 しかしよく分からないと思います。 そこで、宗教界の方には大変申し訳ないのですが、敢えて今の若い人達にも理解できるような表現をします。 無理矢理に今の会社組織で表現す … 続きを読む →
このあと五組の男女一対の神が現れますが、『身を隠したまひき』との説明はありません。 ということは姿形が見えたということになります。 名前を書くとややこしいので一対を(三番)、(四番)、(五番)、(六番)と番号にしておきま … 続きを読む →
前回の宇摩志阿斯訶備比古遅神に続いて登場するのは、 (5)天之常立神(あめのとこたちのかみ) 五番目に登場する神で、「天(てん)」の根元(こんげん)とか永続性を神格化したと解釈されています。 ですからこの神は「高天原」「 … 続きを読む →
実は、『身を隠したまひき』の理由は分かりません。 これまで現れた三柱のあと、以下の二柱の神が現れます。 (4)宇摩志阿斯訶備比古遅神 (うましあしかびひこぢのかみ) 「あしかび」というのは「葦の芽」の意味だそうで、そ … 続きを読む →
【1】で紹介した天之御中主神に続いて登場する神は、 二番目が(2)高御産巣日神(たかみむすひのかみ)、 三番目が(3)神産巣日神(かむむすひのかみ) です。 この二柱の神の名は、「高御」と「神」が違うだけで、「産巣日」は … 続きを読む →
古今東西のフィクション・ノンフィクションとも、登場者には皆それなりの役割があります。 古事記がフィクションであったとしても、同様でしょう。 古事記は、『天皇家が、日本の正当な統率家系であることを証明するために書かれた書物 … 続きを読む →
【9】でも述べましたが、古事記の序は元明天皇を大賛美しています。 それだけ素晴らしい天皇が、天武天皇が指示していた歴史書の編纂を具体的に命じたとしている訳です。 これまで述べてきましたように、38代天智天皇誕生(661年 … 続きを読む →
文武が15歳で天皇となったのは697年、持統は702年に亡くなったとされていますから、持統は約5年間、文武天皇をバックアップできたわけです。 持統が亡くなった時、文武はまだ20歳です。 その5年後、文武天皇は25歳で亡く … 続きを読む →
後継者と目していた息子を亡くした持統天皇は、落胆したはずです。しかし彼女は、悲嘆で泣き暮らすようなナイーブな女性ではありません。 草壁皇子の息子、つまり彼女直系の孫である軽(かるの)皇子を42代文武(もんむ)天皇とします … 続きを読む →